仏文学者の田辺貞之助(たなべ・ていのすけ)氏は、自伝的随筆集『女木川界隈』の中で、生まれ育った故郷である砂村(現在の東京都江東区北砂町)で体験したさまざまな出来事を書き記している。[1]
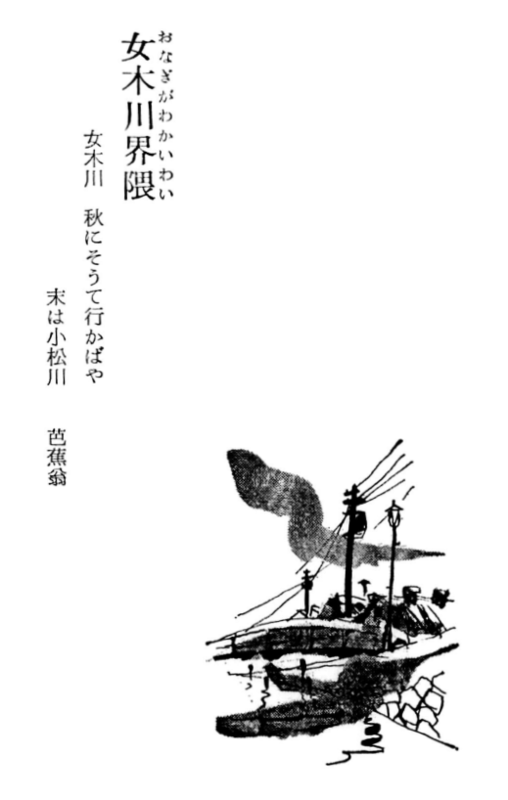
まえがき
江東地区を縦横にはしっていた江戸時代の運河も、いまは大方うめられて、残っているものはあまり多くない。そのひとつに、江東区を西から東へ一直線に断ちきって、隅田川と荒川放水路とをつなぐ小名木川というのがある。この小名木川を、西から三分の二ほどのところで、十間川という別の運河が直角に切っているが、以前はそこが東京市の境で、十間川の東は南葛飾郡だった。砂村は北を小名木川で、西を十間川で仕切られ、東は中川まで、南は東京湾におよぶ、かなりひろい農村だった。この農村は十数の新田にわかれ、むかしは葛西三郎の領地、すなわち葛西領の一部であった。ぼくがこの本のなかでしきりに故郷の名をもって呼ぶのは、この村である。砂村は大正年代に町制をしかれて砂町となり、いまは江東区に属し、北砂町、南砂町にわかれる。ぼくが生れ、この本で語られているのは、主として北砂町五丁目、むかしの亀高新田である。
(略)
小名木川筋には、鶴屋南北も住み、俳聖芭蕉もすみ、『女木川界隈』の項で書いたように、あの土手はこれら文豪の散策の地であったらしい。小名木川そのものも、千葉茨城方面から江戸への水運の要路であった。中川御番所の歴史を見ると、この川の当時の役割があきらかにうかがわれる。古い文書でしらべたら、なお面白いことがいくらも見つかるであろう。昔なつかしい川である。
だが、この本の原稿を書いているとき、こういう消えさった土地の風景をいくら書いても仕方がない。むなしい絵空事とえらぶところがないではないかと、心のどこかでつぶやく声がした。それももっともなことである。しかし、もう一人のぼくはもはや知る人もあまりない故郷の姿を、せめて紙のうえにだけでも再現したい気持でいっぱいだった。そこでついにこの本を書きあげたが、まだ書きたいことが限りもなく胸のなかに渦巻いている。笑うべき老いの繰言ではある。
なお、小名木川は古くは女木川とかかれたようである。現に芭蕉句碑にも女木川とあるので、この本の標題に借用した。いまは黒い濁水の帯と化した小名木川も女木川と書いてみると、昔物語の川のような、情緒あふれる野趣を思わせるからである。
昭和三十七年春
田辺貞之助
田辺氏は、旧制高校1年のときに、この故郷で関東大震災に遭遇した。『女木川界隈』ではこのときの体験に一節を割いているが、この節にはなぜか「新巻の鮭」という題がつけられている。[2]
関東大震災と新巻鮭にいったい何の関係があるのか。それは、最後まで読んでみれば分かる。
猿又ひとつで、茶碗と箸をもって、めしを口へもっていこうとしていた。そこへぐらぐらときたので、とっさに、はだしで縁側からとびだして、裏庭の隅のいちじくの木のしたに逃げた。だが、立っていられないので、地べたへすわった。いまとびだした縁側のしたに、くだけた瓦が山脈をなしていた。棟を越して向うに見える日本製糖の大煙突が二メートルも横にゆれていた。気がついてみると、両手に茶碗と箸をもったままだった。仏さまのご飯のように山盛りによそっためしは、灰色のほこりにまみれていた。ぼくはひどく腹がへっていたので、めしの上っつらを箸でかきおとしてみた。すると、焼けつくような秋の日ざしをうけて、めしが真白く、きらきらとひかった。そこで、ぼくは「腹がすいては、いくさができない」と鼻唄でいいながら、ぐらぐら揺すられながら、そのめしを平らげた。
門の方へにげた父が、胴間声で、「てえこう!てえこう!」と呼んでいた。
「おーい、うらにいるよー」
「なんともなかったかー?」
「うーん、なんともない。いまめしをくってる」
旧制第一高等学校の一年のときだった。九月一日は始業式だけだったので、十一時半ごろかえってきた。あの時分には、ひどい腹っぺらしだったので、母がお膳立てをしてくれるのも待てずに、お鉢をひきよせたのだった。母は糠味噌のおこうこを出していたところだったので、台所の戸棚や壁や柱につたわりながら外へ逃げた。あとから気がつくと、ずーっと糠味噌が筋をひいてはりついていたので、大笑いだった。
だが、地震の被害は大笑いじゃすまされなかった。母屋と家作の屋根の瓦が七分どおりおちてくだけ、壁ははがれ、柱はゆがんだ。大正六年の大津浪の損害がまだなまなましく記憶にのこっているのに、またこの天災だ。あの当時の父の苦労を思うと、気の毒になる。
(略)
三日目になると、朝鮮人が武装して横浜の方から押しかけてくるから、みんな注意しろ。ことに、井戸ヘ毒を投げこむそうだから、井戸の警戒を厳重にしろと、巡査がふれてきた。そこで、めいめい鉄棒や竹槍をもちだし、井戸のまわりに縁台をならべて、徹夜の見張をすることになった。ひどい蚊だったが、宵の口は家作の細君や娘たちもまじって、にぎやかだった。
その時分になると、深川方面の焼出されが幾組も小さな荷物をもって町へはいりこんできた。空地へ竹を四本立て、それへ蚊帳をつるものもあった。「竹の柱に茅の屋根」というが、ちょっといい考えだと感心した。
(略)
地面に風呂敷をしいて、二三十個のタバコをならべて売っている娘もいた。きっとタバコ屋の娘だろう。猛火に追われて、親たちと離ればなれになりながらも、あとの生活のことを考えて、店のタバコをかかえてきたのだろう。だが、あの娘は、タバコを売りつくして、無一物になってしまったら、次にはなにを売るのだろうと、ぼくらはささやきあった。
四日目ぐらいになると、朝鮮人狩りが本格的になった。昼すぎだったと思うが、若い連中の集りにいって帰ってくると、うちの門の柱に、第何分隊屯所と筆太とに書いた紙をはり、剣付き鉄砲の兵隊が立っていた。ぼくはびっくりして、裏木戸からはいり、「どうしたんだい?」と、声をひそめてきくと、母が「今日から兵隊さんが十四五人、うちへとまるんだってさ」と、おどおどしていた。
裏の庭で、兵隊さんが牛蒡剣をみがいていた。縄をひろってきて、それへ砂をつけてこするのだが、刃金にしみこんだ血のしみがなかなかおちない。ぼくがぼんやりそばに立ってみていたら、「アンチャン、磨き砂はねえかな」ときいたので、台所から磨き砂をもっていってやった。それでもしみはおちなかった。磨き砂の入物をもとのところへもどしに行くと、母が「兵隊さん、磨き砂をなんにつかったんだい?」ときくから、これこれだと話すと、母は「まあ、いやだ!」といって、その箱を外へ放りなげた。日ごろお鉢や食器をあらうときにつかう磨き砂だったのである。
(略)
物情騒然とは、あの時分のことをいうのだろう。どこそこでは何人殺された。誰それは朝鮮人と間違えられて半殺しの目にあった。山といわれたら、そくざに川といわないとやられる。そんな話ばかりだった。小名木川には、血だらけの死骸が、断末魔のもがきそのままの形で、腕を水のうえへ突きだしてながれていた。この死骸は引き潮で海まで行くと、また上げ潮でのぼってくると見えて、ぼくは三度も見た。
番小屋につめていたとき、隣りの大島町の六丁目に、たくさん殺されているから見に行こうとさそわれた。そこで、夜があけ、役目がおわると、すぐに出掛けた。
石炭殻で埋立てた四五百坪の空地だった。東側はふかい水たまりになっていた。その空地に、東から西へ、ほとんど裸体にひとしい死骸が頭を北にしてならべてあった。数は二百五十ときいた。ひとつひとつ見てあるくと、喉を切られて、気管と食道と二つの頸動脈がしらじらと見えているのがあった。うしろから首筋をきられて、真白な肉がいくすじも、ざくろのようにいみわれているのがあった。首のおちているのは一体だけだったが、無理にねじ切ったとみえて、肉と皮と筋がほつれていた。目をあいているのが多かったが、円っこい愚鈍そうな顔には、苦悶のあとは少しも見えなかった。みんな陰毛がうすく、「こいつらは朝鮮じゃなくて、支那だよ」と、誰かがいっていた。
ただひとつあわれだったのは、まだ若いらしい女が――女の死体はそれだけだったが――腹をさかれ、六七ヵ月になろうかと思われる胎児が、はらわたのなかにころがっていた。が、その女の陰部に、ぐさりと竹槍がさしてあるのに気づいたとき、ぼくは愕然として、わきへとびのいた。われわれの同胞が、こんな残酷なことまでしたのだろうか。いかに恐怖心に逆上したとはいえ、こんなことまでしなくてもよかろうにと、ぼくはいいようのない怒りにかられた。日本人であることを、あのときほど恥辱に感じたことはない。
石炭殻の空地のわきに、何々牧場とかいて、丸太のかこいのなかに雌牛が七八頭いた。そこで、生牛乳をうっていた。東京が全滅して牛乳が出せないので、臨時に店売りをしていたらしい。こいつはありがたいというので、みんなではいっていった。一合二銭だった。上衣のポケットをさぐると十銭玉がひとつあったので、ぼくは五合たのんで、ぐいぐいのんだ。徹夜の夜番のあとの冷い牛乳は、まさに甘露の味だった。一週間にわたる栄養の不足も、これで取りかえせるかと思った。
だが、いい気持になって外へ出た途端に、血の匂いがむっと鼻をついた。と同時に、五合の牛乳をガッと吐いてしまった。さっきは、飲まず食わずの夜警で、鼻の粘膜がからからにかわいていたので、血の匂いがわからなかったのだろう。それを牛乳でうるおしたので、敏感に感じとったにちがいない。惜しいことをした。
性器に竹槍を刺された女性の惨殺死体は、湊七良氏の証言[3]の中にも出てくる。山岸秀氏は、
女性の陰部へ竹槍を刺したという目撃証言は、場所が特定できるものは江東のもの。したがっておそらく一つの事件、行為が複数の口で語られ、伝聞されていった結果であろう。
と推定している[4]が、湊氏がそれを見たのは亀戸の五ノ橋であり、同じ江東区といっても場所が違う。また、田辺氏が二百五十もの虐殺死体の中の一つとして語っているのに対して、湊氏の証言には他の死体のことはまったく出てこない。従って、この二つは別々の事件である。
この江東区大島町での大量殺戮事件は、虐殺への軍隊の関与が公文書上で確認できる数少ない事例の一つでもある。「関東戒厳司令部詳報」所収の「震災警備ノ為兵器ヲ使用セル事件調査表」に、次の記載[5]がある。
| 隊 号 | 野重一及騎十四 |
| 時 日 | 九月三日午後三時頃 |
| 場 所 | 大島町八丁目付近 |
| 軍隊関係者 |
野重一ノ二砲兵少尉IK以下六十九名 |
| 兵器使用者 |
騎十四騎兵卒三名 |
| 被兵器使用者 | 鮮人二百名(氏名不詳) |
| 処 置 | 殴打 |
| 行動概況 |
大島町付近人民力鮮人ヨリ危害ヲ受ケントセル際救援隊トシテ野重一ノニI少尉来着シ騎十四ノM少尉卜偶々会合シ共二朝鮮人ヲ包囲セントセルニ群衆及警官四五十名約二百名ノ鮮人団ヲ率ヰ来リ其ノ始末協議中騎兵卒三名力鮮人首領三名ヲ銃把ヲ以テ殴打セルヲ動機トシ鮮人ハ群衆及警官卜争闘ヲ起シ軍隊ハ之ヲ防止セントシカ鮮人ハ全部殺害セラレタリ |
| 備 考 |
一、野重一ノニ将校以下六十九名ハ兵器ヲ携帯セス 二、鮮人約二百名ハ暴行強姦掠奪セリト称セラレ棍棒 三、本鮮人団ハ支那労働者ナリトノ説アルモ軍隊側ハ |
田辺氏が書き留めた「こいつらは朝鮮じゃなくて、支那だよ」という発言や、調査表の備考欄にある「本鮮人団ハ支那労働者ナリトノ説アルモ軍隊側ハ鮮人卜確信シ居タルモノナリ」という奇妙な記述が暗示しているように、この事件の被害者は実は朝鮮人ではなく、中国人労働者たちだったことが明らかになっている。[6]
大島町事件
黄子蓮はもともと300人あまりの同郷の者たちと大島五丁目の林合記客桟(旅館)に住んでいたのだが、1日の地震で家が倒壊したので、2日同郷の者たち174人と八丁目の林合吉客桟に移転してきた。
「9月3日昼ごろ、八丁目の宿舎に大勢の軍隊、警察、青年団、浪人たちがやってきて、『金を持っているやつは国に帰してやるからついてこい』といって174人を連れ出し、近くの空き地へ来ると「地震だ、伏せろ!」といって全員を地に伏せさせ、手にした棍棒、鳶口、つるはしなどで殴り殺した。私は殴られて気を失ったので死んだと思われて捨て置かれた。夜中に痛みのために目を覚まし、死体の中をはうようにして蓮池のそばで一昼夜を過ごし、5日に七丁目の空き家に逃げ込んだところをまた暴徒に殴られた。七丁目の駐在によって小松川署に送られ、さらに習志野収容所に送られて10月に帰国した」という。この時、現場を目撃した木戸四郎は、「5、6名の兵士と数名の警官と多数の民衆は200名ばかりの支那人を包囲し、民衆は手に手に薪割り、鳶口、竹槍、日本刀、等をもって、片端から支那人を虐殺し、中川水上署の巡査のごときも民衆と共に狂人のごとくなって、この虐殺に加わっていた。2発の銃声がした。あるいは逃亡者を射殺したものか、自分は当時わが同胞のこの残虐行為を正視することができなかった」と11月18日、現地調査に来た丸山伝太郎らに話している。
(略)
この3日の朝、大島町八丁目付近の住民は外へ出るなと命じられていた。午前8時、2発の銃声がとどろいてそれが合図であるかのように剣付き鉄砲の兵士2人が、大島六丁目の中国人宿舎に来て、中国人労働者たちを屋外に整列させ、八丁目の方へ裏通りを引き立てて行った。大勢の民衆が兵士たちと共に取り囲んで行くのを、「どこに連れていかれるのだろう」と近所の主婦たちが見ていた。(丸山らの調査報告)
(略)
午後3時ごろ、野重第1連隊第2中隊の岩波少尉以下69名、騎兵14連隊三浦孝三少尉以下11名は、群集と警官4、50名が「約200人の鮮人団を連れてきてその始末を協議中」のところへ行き合わせて全員殺害した。(略)
大島八丁目に住む岩崎留次郎さん(10年前はご健在で92歳。その年他界)は、当時七丁目に住んでいて、9月3日は、避難民のための炊き出しの世話に追われて、夕方虐殺現場に出かけるのだが、「中国の人々は幾重にも取り囲まれて逃げられるような状況ではなかったよ。無残なことだった」と語る。この騒ぎは日が暮れるまで続いたのである。
中国人に関しては暴動の流言飛語が流されていたわけでもないのに、なぜ彼らはこのような無残な殺され方をしなければならなかったのか。この事件は、混乱の中で兵士や民衆が逆上した結果ではなく、どうやら計画的大量殺人だったらしいのだ。[7]
関東大震災時の中国人虐殺の研究を続けた仁木ふみ子は、その背景に人夫請負人(労働ブローカー)の意図があったと推理している。第一次世界大戦に伴う好況も終わり、数年前から不況が始まっていた。日本人より2割も安い賃金で働く中国人労働者の存在は、日本人労働者にとっても、彼らを手配し、賃金をピンハネする労働ブローカーにとっても目ざわりであり、排斥の動きが起こっていた。一方、中国人を安く使っていた日本人ブローカーにとっても、後述する僑日共の指導によって未払い賃金の支払い要求などを起こすようになった中国人は、もはや使いにくい存在になっていた。
警察も中国人労働者を好ましく思っていまかった。当時の大島町を管轄する亀戸署は、管内に労働争議の多発する工場を多く抱えていることから、公安的任務を強く負った署であった。そのうえ中国人にまで労働運動を起こされてはたまらない。行政レベルでも、日本人労働者保護のためとして、中国人労働者の入国制限・国外退去などを進めつつあった。
労働ブローカーと警察が、朝鮮人虐殺で騒然としている状況に便乗して、日本人労働者をけしかけ、さらに「朝鮮人暴徒鎮圧」の功を焦る軍部隊を引き込み、中国人追い出しというかねての悲願を実行に移したのだ――というのが、仁木の見立てである。(略)
警視庁は翌日には事件の概要を把握しており、現場検証を行っている。田辺氏が見た「頭を北にして並べてあった」死体は、検死後のものである。
では、『女木川界隈』に戻ろう。
その翌朝だった。ぼくはやはり番小屋につめていた。毎日、玄米の小さなむすびと梅干だけだったので、腹がすききっていた。そこへ、明け方の四時ごろだったろうか。脂っこい、新鮭をやくような匂いがながれこんできた。いままで、あんなにうまそうな匂いをかいだことがない。豊潤といおうか、濃厚といおうか。女の肌でいえば、きめのこまかい、小麦色の、ねっとりした年増女の餅肌にたとえたいような匂いだった。それでいて、相当塩気がきいた感じで、その匂いだけで茶漬がさらさらくえそうだった。ぼくは思わず生唾をのんだ。腹がぐうぐう鳴った。だが、その音はぼくの腹だけから出たものではなかったらしい。
「うまそうな匂いだね」と、ぼくは思わずいった。
「まったくだ。新巻の鮭だ!」
「誰がいまごろ焼いてやがるんだろう。いまいましい奴だ。押しかけていこうか」と、誰かが真剣な口調でいった。
ぼくらはたまりかねて、みんな外へ出た。まるで九十九里浜へよせる高波のように、例の匂いがひたひたと町じゅうをつつんでいた。しかも、番小屋のなかでかいだより数倍もつよく、むっと胸にこたえるような匂いだった。
「こりゃ、鮭じゃないぞ」と、誰かがいった。「鮭にしちゃ匂いがつよすぎるし、一匹まるごと焼いたって、こんなに匂いがひろがるはずはない」
ぼくらはしばらく棒立ちになって、いまは不気味な気持で、その匂いをかいでいた。
一人が急に叫んだ。
「わかった!あの匂いだ!」
「なんの匂いだ?」
「なんの匂いだ?」
「ほら、きのう見にいった、あの死骸をやいているんだ!」
その途端に、ぼくはむっとなにかが胸にこみあげてきて、腰の手拭で口をおさえながら、番小屋のうしろへ駆けこんだ。
虐殺死体は警察の指揮の下、大島の仕事師田中伝五郎が人夫たちを使って焼却した。日本政府は白を切り通し、事件は隠蔽された。[8]
ちなみに、田辺氏は『潮』71年9月号にも談話を寄せていて、次のように語っている。[9]
しかも、朝鮮人の暴挙のほうは、ウワサばかりで、じっさいには一つも見かけなかった。結局あのパニック状態の中で、為政者は民衆の不安を他へ転化させる必要があり、その仮想敵国として朝鮮人が利用されたのだろう。政治家のよくつかう手段である。(略)
しかし、あれからすでに半世紀、戦後生まれが人口の半分を占めるようになったいま、あの事件も過去のこととして消え去ろうとしている。それはそれでいいとぼくは思う。“臭いものにフタをしろ”という意味でなく、このままいまわしい過去を知る人もなくなり、二度とああいうことが起きなければ理想的ではないか。これは日本人の身勝手といわれるかもしれないが……。(談)
残念ながら、この田辺氏の意見には賛成できない。反省することなく忘れて済まそうとする者は、必ずまた同じ過ちを繰り返すからだ。現に、「過去を知る人」がいなくなっていくのをいいことに、忌まわしい過去の歴史から目をそらし、それどころか歴史上の事実を改竄し、過ちに満ちていたあの暗黒時代に引き戻そうとする愚か者たちばかりがはびこっているのがこの国の今ではないか。
[1] 田辺貞之助 『女木川界隈』 実業之日本社 1962年 P.1-4
[2] 同 P.99-108
[3] 湊七良 『その日の江東地区』 労働運動史研究37号(1963年7月) P.30-32
[4] 山岸秀 『関東大震災と朝鮮人虐殺』 早稲田出版 2002年 P.103-104
[5] 松尾章一監修 『関東大震災政府陸海軍関係資料 II巻 陸軍関係資料』 日本経済評論社 1997年 P.161
[6] 仁木ふみ子 『あの時何がおこったのか 大島町事件・王希天事件の実相』 中帰連26号(2003年秋) P.15-16
[7] 加藤直樹 『九月、東京の路上で 1923年関東大震災ジェノサイドの残響』 ころから 2014年 P.63-64
[8] 中帰連 P.17-19
[9] 『日本人一〇〇人の証言と告白』 潮 1971年9月号 P.98




