前回記事で紹介したような、中国戦線で様々な残虐行為に手を染めてきた兵士たちは、その後どんな人生を送ったのだろうか。
敗戦後には連合軍によるBC級戦犯裁判が行われたが、中国での戦争犯罪に関する裁判は極めて限定的なものでしかなかった。いかに被害が甚大であっても、個々の事件について犯人を個人として特定できる証拠がほとんど残されていなかったためだ。中国国民政府による裁判で訴追された日本人戦犯はわずか883人、うち有罪判決を受けた者は504人しかいない。しかも服役者のすべてが、国共内戦による混乱の中、1949年2月には日本に送還されている。[1]
南京大虐殺に関してさえ、有罪(死刑)判決を受けた者は、東京裁判で裁かれた松井石根(中支那方面軍司令官)、南京軍事法廷で裁かれた谷寿夫(第六師団長)、向井敏明、野田毅、田中軍吉の5名しかいない。向井と野田は「百人斬り競争」、田中は「三百人斬り」で新聞報道されたりして有名になってしまい、言い逃れができなかったからで、それ以外の「無名の」虐殺者たちはすべて処罰を免れたわけだ。
こうして元兵士たちは、戦友会による箝口令などに守られて世間的な非難を浴びることもなく、戦後の長い時間を平穏無事に過ごすことができた。おそらく、時間が経つにつれ、自分がやったことを思い出すこともなくなっていったのだろう。
しかし、結局のところ、人間は自分に嘘をつき通すことはできない。
だから、何気ない会話をきっかけに、こんなことになってしまうこともある。

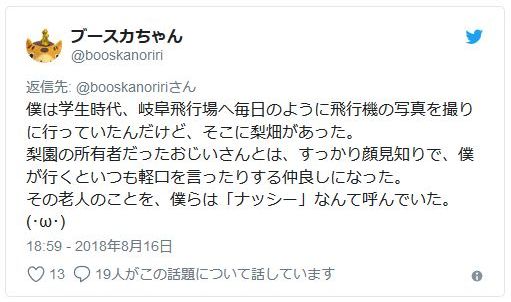


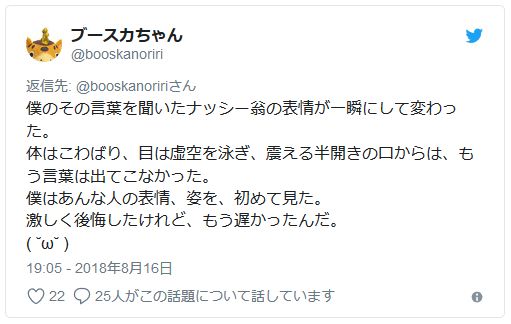

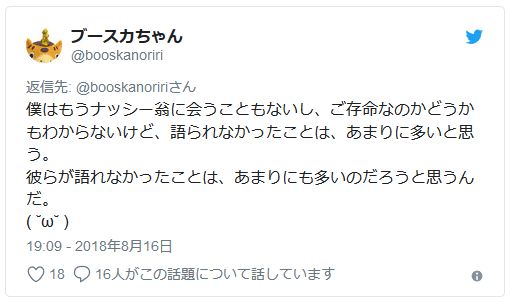
また、年老いて心身が衰え、近づいてくる自身の死に向き合わなければならなくなると、人は嫌でも自分の人生とは何だったのか、自分は何をしてきたのかを思い起こさざるを得なくなる。
保阪正康氏が、京極夏彦氏との対談の中で、そんな兵士たちの晩年についてこう語っている。[2]
保坂 (略)僕は医学システムの評論やレポートなんかも書くから医者からよく相談されるんですけど、八十代で死にそうなおじいさんがいるというんですよ。
京極 ほう。
保坂 四十代の医者が僕のところにきて、もう動けないはずの患者が、突如立ち上がって廊下を走り出すというんですよ。そして、訳わかんないことを言って、土下座してしきりにあやまるというんです。そういう人たちには共通のものがある。僕はこう言うんです。「どの部隊がどこにいって戦ったかというのを、だいたいは僕はわかるから、患者の家族に所属部隊を聞いてごらん」。みんな中国へ行ってますよ。医者はびっくりします。
京極 ひどいことをしたのをひた隠しにして生きて来られたんですね。
保坂 それを日本はまだ解決していない。
人を殺す、とりわけ無抵抗の相手を殺すという行為は、やってしまえばもう取り返しがつかない。銃剣が肉を突き通す感触も、吹き出す血の色も、呆然と自分を見つめる相手の眼の光も、忘れたつもりになることはできても、真に忘れることなどできないのだろう。
侵略戦争とは、死を前にしてこんな苦しみを味合わなければならない人間を量産する行為でもある。
[1] 林博史 『BC級戦犯裁判』 岩波新書 2005年 P.102~106
[2] 『スペシャル対談 京極夏彦×保阪正康』 IN・POCKET 2003年9月号 講談社 P.30-31

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 [Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本](https://m.media-amazon.com/images/I/51cfj-Om48L._SL500_.jpg)